「コンセンサス」とは、「意見の一致。合意。」という意味があります。
しかし、コンセンサスの意味がわかったところで、その正しい使い方やシチュエーションを理解しておかないと、間違った解釈をしたまま恥ずかしい思いをするかもしれません。
そうならないように、この記事でコンセンサスの意味に加えて、正しい使い方を例文も交えてわかりやすく解説しておりますので、最後まで読んでこれから活用できるようにしてくださいね!
 ヒロト
ヒロト今回のプロジェクトの進め方について、みんなのコンセンサスを取る必要があるね。
 コトハ
コトハそうね。全員が納得できる形にするために、意見をまとめる時間を作ったほうがいいかも。
「コンセンサス」の意味とは?わかりやすく解説
「コンセンサス」とは、意見の一致。合意。という意味があります。
コンセンサスの意味を辞書で調べると、このように解説されております。
【コンセンサスの意味】
goo辞書より引用
- 意見の一致。合意。「社内の—を得る」
「コンセンサス」の意味
「コンセンサス(consensus)」とは、「みんなの意見が一致すること」や「合意に達すること」を意味する言葉です。特に、グループや組織で話し合いをして、全員または大多数が納得できる結論に至ることを指します。日本語では「合意」や「総意」と言い換えられることが多いです。
「コンセンサス」の意味の概要
「コンセンサス」は、ただ意見をそろえるだけでなく、全員が納得しやすい形で決定することを重視します。例えば、会社の会議や学校のグループ活動などで、異なる意見を持つ人たちが話し合いながら、お互いに納得できる結論を見つけるときに使われます。全員が100%同じ考えになる必要はなく、反対意見があっても、最終的に大多数が同意すれば「コンセンサスが得られた」と言えます。
 ヒロト
ヒロト「コンセンサス」ってどんなことを意味するの?もう少し詳しく教えて!
 コトハ
コトハ「コンセンサス」とは、複数の人が集まって何かを決めるときに、全員が納得し合意することを意味します。
「コンセンサス」の語源や由来
コンセンサスの語源や由来は以下のとおりです。
【コンセンサスの語源や由来】
weblioより引用
- 「コンセンサス」は、英語の名詞 consensus に直接由来する語である。この英語の consensus は、ラテン語の consentire を語源とする。このラテン語の consentire は「con(共に)+sentire(感じる)」という構成の言葉である。
「コンセンサス」の語源や由来
「コンセンサス(consensus)」は、もともとラテン語の「consensus(コンセンスス)」からきています。この言葉は、「共に(con)」+「感じる(sentire)」という意味を持つラテン語が組み合わさったものです。つまり、「みんなが同じ気持ちになる」「心が一つにまとまる」という意味を表しています。
この言葉が、のちに英語の「consensus(コンセンサス)」になり、「意見の一致」「合意」という意味で使われるようになりました。英語では政治やビジネスの場面で、多くの人の意見をまとめるときによく使われます。
日本では、ビジネスの世界や会議などで「コンセンサスを取る」という言い方をすることが一般的になりました。これは、「全員が納得できる結論を出す」という意味で使われています。特に、みんなの意見を尊重しながら決めることが重要な場面で、「コンセンサス」が求められるようになったのです。
このように、「コンセンサス」は、昔から「みんなの気持ちや意見を合わせる」という考え方を大切にしてきた言葉なのです。
「コンセンサス」の使い方を例文でわかりやすく解説
それでは、「コンセンサス」の正しい使い方を具体的にイメージできるようわかりやすい例文をご紹介します。
 ヒロト
ヒロトコンセンサスってどういう場面で使ったりするの?
 コトハ
コトハ「コンセンサス」は、意見をまとめる場面で使われます。例えば、ビジネスの会議では、新しいプロジェクトの方針を決めるときに「チームのコンセンサスが得られた」と言います。学校のグループ活動では、文化祭の企画を決めるときに「クラス全員のコンセンサスを取る」と表現できます。政治や国際会議では、各国が話し合って共通の結論を出すときに「環境対策についてコンセンサスが形成された」と使います。
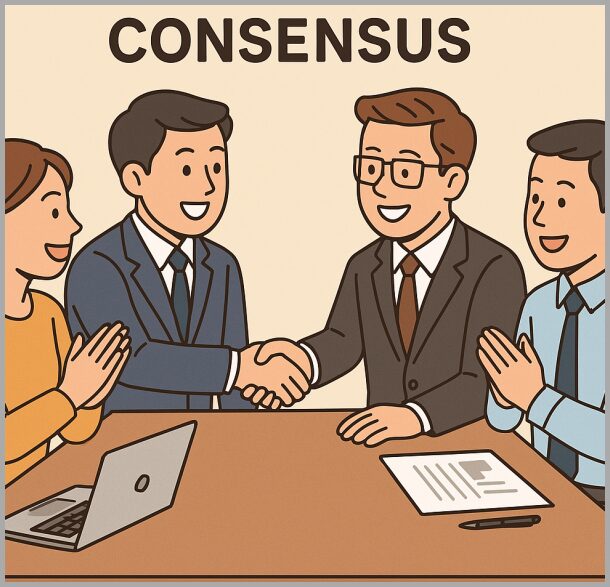
「コンセンサス」は、意見をまとめる場面や、みんなで決めごとをするときによく使われます。具体的には、以下のような場面で使われます。
- ビジネスの会議
会社のプロジェクトや新しいルールを決めるときに、社員の意見をまとめる場面。 - 学校のグループ活動
クラスで文化祭の出し物を決めるときや、グループの意見を統一するとき。 - 政治や国際会議
環境問題や経済政策について、各国の代表が話し合い、共通の考えを持つとき。 - 家族や友人との話し合い
旅行の行き先や食事のメニューなど、複数の人で意見を合わせるとき。 - 地域の会合やイベント企画
町内会やPTAなどで、行事の内容を決めるとき。
「コンセンサス」を使うときには、以下の点に注意しましょう。
- 全員が100%同じ意見でなくてもよい
反対意見があっても、大多数が納得すれば「コンセンサスが得られた」と言える。 - 多数決とは違う
「コンセンサス」は、ただ数で決めるのではなく、できるだけみんなが納得できるように話し合うことが大切。 - 状況によっては時間がかかる
意見が分かれる場合、話し合いを何度も重ねる必要があるため、すぐに決まらないこともある。<注意点1
コンセンサスの例文①
会社の会議で、新しい商品を作るかどうかを決める場面です。みんなの意見がまとまり、コンセンサスが取れました。
 ヒロト
ヒロト新商品の開発について話し合った結果、チーム全員のコンセンサスが得られた。
 コトハ
コトハそう、よかった!これでプロジェクトを進めることができるわね。
 ヒカル
ヒカルこの例文では、「チーム全員のコンセンサスが得られた」という表現を使っています。これは、「全員が納得する形で意見がまとまった」という意味です。会社では、決定をするときに「コンセンサスを取る」ことがよくあります。
コンセンサスの例文②
クラスで文化祭の出し物を決める話し合いをしている場面です。最初は意見が分かれていましたが、最終的にコンセンサスが取れました。
 ヒロト
ヒロト文化祭の出し物について、クラス全員で話し合い、コンセンサスを取ることができた。
 コトハ
コトハよかった!楽しい文化展になるといいわね!
 ヒカル
ヒカルこの例文では、「クラス全員で話し合い、コンセンサスを取ることができた」と表現しています。これは、「クラスのみんなが納得できる結論が出た」という意味になります。学校のグループ活動では、意見をまとめるためにコンセンサスを取ることが大切です。
コンセンサスの例文③
国際会議で、環境問題について話し合い、各国が共通の意見に合意する場面です。
 ヒロト
ヒロト環境保護について、各国の代表がコンセンサスを形成し、新たな取り組みを始めることになった。
 コトハ
コトハ環境保護問題は各国共通の重要な問題ね。
 ヒカル
ヒカルこの例文では、「コンセンサスを形成し」という表現を使っています。これは、「各国の代表が話し合いを重ねて、共通の意見を持つようになった」という意味です。政治や国際会議では、対立する意見が多いため、コンセンサスを取るのに時間がかかることもあります。
「コンセンサス」の言い換え表現を例文を使ってわかりやすく解説
「コンセンサス」は、「合意」や「意見の一致」を意味する言葉ですが、日常的に使うもっと簡単な表現もあります。ここでは、特にわかりやすい言い換え表現を2つ紹介します。
【コンセンサスの言い換え表現】
- まとまった意見
- みんなの同意
「まとまった意見」の例文
「まとまった意見」は、「グループ内で話し合った結果、みんなが納得できる意見」という意味です。「コンセンサス」とほぼ同じ意味で、日常会話でも使いやすい表現です。
クラスで文化祭の出し物を決めるとき、最初は意見が分かれていましたが、話し合いを重ねて「まとまった意見」が出た場面です。
 ヒロト
ヒロトクラスの文化祭の出し物について、まとまった意見が出たので、先生に伝えることになった。
 コトハ
コトハどんな出し物にまとまったのか楽しみ!
 ヒカル
ヒカル「コンセンサスが取れた」と言い換えることもできますが、「まとまった意見」のほうが、より親しみやすい言葉で、日常会話や学校の話し合いで使いやすい表現になります。
「みんなの同意」の例文
「みんなの同意」は、「関わっている人たちが話し合い、納得してOKを出すこと」を表します。「コンセンサス」は少しフォーマルな表現ですが、「みんなの同意」は日常的な場面で使いやすい言葉です。
友達と旅行の計画を立てるとき、行き先について話し合い、「みんなが納得したら予約しよう」と決めた場面です。
 ヒロト
ヒロト旅行の行き先を決めるために、みんなの同意を得てから予約をすることにした。
 コトハ
コトハみんなどこに行きたいのかしら?
 ヒカル
ヒカル「みんなの同意」はよりカジュアルな表現なので、友人や家族との会話で使いやすいです。
「コンセンサス」は、フォーマルな場面でも使われる言葉ですが、日常会話では「まとまった意見」や「みんなの同意」と言い換えると、より親しみやすくなります。場面によって適切な言葉を使い分けることで、スムーズなコミュニケーションができます。
「コンセンサス」の類義語
「コンセンサス」と似た意味を持つ言葉はいくつかあります。ここでは、特に「合意」と「アグリーメント」の2つを紹介します。それぞれの言葉の意味や使われる場面、違いについても解説します。
【コンセンサスの類義語】
マイナビニュースより引用
- 合意(ごうい):「各自の意見を一致させる」という意味の言葉。
- アグリーメント:「意見や方針に同意や賛同を示す」という意味の言葉。
「合意」の例文
合意(ごうい)とは、「2人以上の人が話し合い、お互いに納得して決めること」を意味します。「コンセンサス」とほぼ同じ意味ですが、「合意」は少人数の話し合いにも使えるのが特徴です。一対一の交渉や契約などでも使われます。
企業同士の契約交渉場面です。
 ヒロト
ヒロト会社と取引先の間で、新しい契約内容について合意に達した。
 コトハ
コトハ契約が成立してよかった!
 ヒカル
ヒカル「コンセンサス」はより多くの人が関わる場面で使われることが多いです。一方、「合意」は2者間の話し合いにも適しているため、法律や契約の分野でもよく使われます。
「アグリーメント」の例文
アグリーメント(agreement)は、英語で「合意」や「契約」を意味する言葉です。ビジネスや法律の文書などでは「アグリーメント」という言葉がよく使われます。意味は「コンセンサス」と似ていますが、正式な契約や書類上の合意を指すことが多いのが特徴です。
仕事のプロジェクトで、チームメンバーが正式に合意を結んだ場面です。
 ヒロト
ヒロトこのプロジェクトの進行について、チーム全員でアグリーメントを結んだ。
 コトハ
コトハよかった!みんなの意見がまとまったのね。
 ヒカル
ヒカル「アグリーメント」はより公式な合意や契約というニュアンスが強くなります。特に、ビジネスや法律の場面で使われることが多い言葉です。
「コンセンサス」の対義語
コンセンサス(consensus)には明確な対義語はありませんが、みんなで意見をまとめることの反対の考え方を持つ言葉として、「独断」と「裁量」があります。
【コンセンサスの対義語】
マイナビニュースより引用
- 独断(どくだん):まわりの意見を聞かずに、自分だけの考えで決めること。
- 裁量(さいりょう):他の人と相談せず、自分の判断で決めることができる権限。
「独断」の例文
独断(どくだん)とは、まわりの意見を聞かずに、自分一人の判断で物事を決めることです。「コンセンサス」はグループの意見をまとめることを重視しますが、「独断」は他の人の考えを無視し、自分の考えだけで決定を下す点が異なります。
会社の部長が、チームのメンバーと話し合わずに、一人で新しいルールを決めてしまった場面です。
 ヒロト
ヒロト部長は、チームと相談せずに独断で新しいルールを決めてしまった。
 コトハ
コトハえー、ひどい!そんなのダメよ。
 ヒカル
ヒカル「コンセンサスが取れていない」状態なので、チームのメンバーは戸惑うかもしれません。ビジネスや組織の中では、独断で決めることが問題になることが多く、「コンセンサスを取る」ことが求められます。
「裁量」の例文
裁量(さいりょう)とは、決定権を持つ人が、自分の判断で自由に決めることです。独断とは違い、「ある程度の権限を持つ人が、自分の考えで決める」という意味で使われます。「コンセンサス」がグループの意見をまとめるのに対し、「裁量」は特定の人が決定する権限を持っていることを意味します。
プロジェクトの進め方について、チームで話し合うのではなく、リーダーが一人で決める場面です。
 ヒロト
ヒロトこのプロジェクトの進め方は、リーダーの裁量に任されている。
 コトハ
コトハリーダーがすべて決めてしまうってこと?
 ヒカル
ヒカル「コンセンサスを取る」とは違い、リーダーの判断で自由に決めることができるため、チームの意見が反映されない場合もあります。ただし、「裁量」があることで、素早い判断が求められる場面ではメリットになることもあります。
「コンセンサス」は、話し合いをして意見をまとめることを重視する言葉ですが、「独断」は一人で決めること、「裁量」は決定権のある人が自由に判断することを指します。どちらもコンセンサスとは反対の考え方ですが、場面によって適切に使い分けることが大切です。
「コンセンサス」の英語表現
「コンセンサス」は、英語でも「consensus(コンセンサス)」と表現されます。
【コンセンサスの英語】
DMM英会話より引用
- consensus:「合意」「総意」
「consensus」の例文
「コンセンサス」は、英語でも「consensus(コンセンサス)」と表現されます。意味は日本語と同じで、「多くの人の意見がまとまること」「合意」「総意」を指します。英語の「consensus」も、ビジネスや政治、学校など、さまざまな場面で使われます。
 ヒロト
ヒロトコンセンサスを英語で表現した例文を教えて!
 コトハ
コトハ"After a long discussion, the team finally reached a consensus on the project plan."のように表現することができます。
日本語訳:長い議論の末、チームはついにプロジェクト計画についてコンセンサスを得た。
 ヒカル
ヒカルこの例文では、reach a consensus(コンセンサスに達する)というフレーズを使っています。「reach a consensus」は、「話し合いをした結果、合意に至る」という意味で、英語でよく使われる表現です。
※例えば、会社の会議やグループでの話し合いで、意見が分かれていたけれど、最終的に全員が納得する決定ができたときに使います。日本語の「コンセンサスを得る」と同じように、英語でも「reach a consensus」という表現が自然です。
このフレーズを覚えておけば、英語のビジネスシーンや学校のディスカッションで役立ちます。
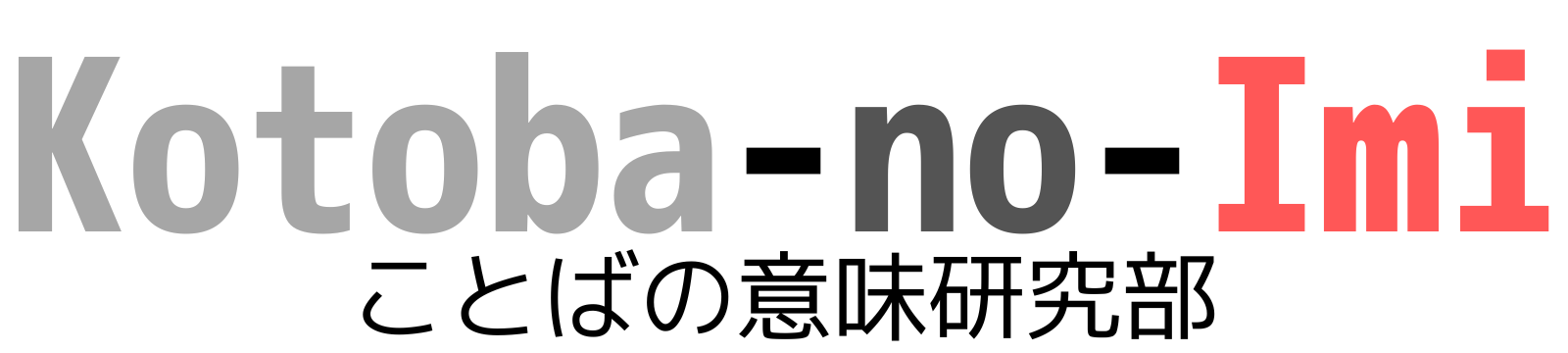

コメント